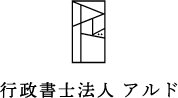葬儀の日程は、葬儀社の手配を行った後に決まるのが一般的です。病院で亡くなった場合は、すぐに遺体を搬送する必要があるほか、死亡診断書を発行してもらうなどタイトな日程で行います。
喪主は配偶者など血縁関係の近しい関係の人が務めるため、精神的にもつらい状況で葬儀の日程を決めることになり負担が大きくなってしまいます。実際には葬儀社が主導となって決めることがほとんどですが、葬儀の日程目安や必要な手続き確認事項などを事前にチェックしておくことがおすすめ。
ここでは、ご逝去から葬儀までの一般的なスケジュールなどについて解説します。
一般的な葬儀までの日程目安
-
- 1日目ご逝去
- 故人が亡くなった日は、葬儀社へ連絡し葬儀場の予約など葬儀日程の相談を行います。また、遺体搬送や安置など葬儀前の準備を行います。
-
- 2日目通夜
- 通夜は故人が亡くなった日の翌日、もしくは翌々日の夕方から夜に行うことが一般的です。通夜のあとは通夜振る舞いや会食を行う場合もあります。
-
- 3日目葬儀
- 葬儀は通夜の翌日に行うことが一般的です。時間は午前中か午後の早い時間に行うことがほとんど。葬儀と同日に火葬を行うことも多いことが
葬儀を行ってはいけない日は?

葬儀の日程として避けた方が良いと言われる日も存在します。実際に避けた方が良いと言われる日とは、日本では古くから伝承されている六曜(ろくよう)と言われる日にちの吉凶を占う指標に基づいた日の中にあります。
「先勝」、「友引」「先負」、「仏滅」「大安」「赤口」の6つが六曜と呼ばれており、それぞれ。その日にやってはいけないことを考える指標です。
中でも「友引」が葬儀を避けた方が良いとされる日で、「友引」とは友人を引き込むとされています。
そのため、火葬場が休業する場合があるため「友引」の日には葬儀を行えない場合もあります。
事前に火葬場の定休日を確認することをおすすめします。
また、「仏が滅びるような凶日」を意味する「仏滅」は、お祝いごとが行われることが少ないですが、通夜、葬儀は故人の冥福を祈るもののため、行っても問題はありません。
葬儀日程の決め方ガイド

①親族・葬儀社への連絡
故人が逝去した場合はすぐに近親者へ連絡をします。病院で亡くなった場合は「死亡診断書」を発行してもらいましょう。
また、葬儀社にもすぐに連絡を行います。病院からすぐにご遺体を搬送しなければならない場合が多いため、すぐに葬儀社と打ち合わせを行います。
②遺体の搬送と安置
病院でなくなった場合は、遺体を病院の霊安室から搬送し、自宅などで安置をする必要があります。遺体は逝去後に24時間以上経過をしなければ火葬できないと法律で定められているため、一度安置をする必要があります。
安置場所は自宅のほか、葬儀社や斎場の安置所などでも可能です。
葬儀社や斎場で安置をする場合は費用が発生しますが、遺体の保全処置をしてもらうことができるため、安心です。
葬儀社に依頼をすれば、病院からの寝台車でご遺体を搬送することもできます。
③葬儀日程の打ち合わせや手配
ご遺体を安置した後は、葬儀の日程や内容について打ち合わせを行います。具体的に決めることと、手配は以下を確認してください。
■手配
・病院で発行してもらう死亡診断書を役所に持参し死亡届を提出
・死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る
・火葬場の空き状況を調べ、予約を行う
・お寺のスケジュール確認と住職の手配
・参列者のスケジュール確認
・遺影準備と写真選別
■決めること
・喪主を誰が務めるか
・葬儀の形式
※一般葬、家族葬、一日葬など
・参列者の人数や予算
・火葬までの流れ
上記の通り死亡届の提出や火葬場の空き状況の確認、お寺のスケジュールなど手配や確認することが沢山あります。
精神的なストレスもあるため1人で考えず、親族や葬儀社に相談をするか、事前に死後事務委任サービスを利用し決めることで負担が軽減できます。
葬儀日程表の作成と送付
葬儀の日程が決定した後は、故人が亡くなったことを親族や友人、仕事関係の方などに葬儀日程の案内状を送ります。
案内状には以下の項目を記載し早めに案内を送るようにしましょう。
・故人の名前
・享年
・逝去の日時
・葬儀(通夜・告別式)の日程
・葬儀場の名前と住所
・喪主の名前と続柄
葬儀日程に関するまとめ
ご逝去から葬儀の日程を決めるまでのスケジュールを解説しました。大切なご家族が亡くなった時は、悲しみの中で準備を始めなければならないため、負担が大きくなってしまいます。
家族や親族、葬儀社と相談をしサポートをしてもらいながら日程を決めていきましょう。
また、負担軽減のためにも事前に葬儀の流れについて相談・委託できる死後事務委任サービスも検討してはいかがでしょうか。
監修

- 行政書士・弁護士
-
法的準備は、安心した生活の基盤になりますし、将来の手続負担の軽減にもつながります。手続きを知り、備えることで、自分らしく生きるきっかけになればと思い、生前のサポートを充実させることを大切にしています。
遺言書の作成や、死後の手続支援(死後事務委任)、不動産に関する手続きなどについて、相続専門の行政書士法人として、幅広く情報提供をさせていただき、一人一人の生活に合った選択肢を一緒に考えてきます。
最新の投稿
 永代供養2024年12月28日永代供養墓とは?種類や必要性、そして歴史・選び方まで徹底解説!
永代供養2024年12月28日永代供養墓とは?種類や必要性、そして歴史・選び方まで徹底解説! 葬儀2024年12月26日葬儀の流れを徹底解説。事前準備や基礎知識、葬儀社選び、葬儀後の手続きを紹介
葬儀2024年12月26日葬儀の流れを徹底解説。事前準備や基礎知識、葬儀社選び、葬儀後の手続きを紹介 お部屋の片付け・遺品整理2024年10月29日葬儀に参列する際に知っておきたい服装や香典のマナーを詳しく解説
お部屋の片付け・遺品整理2024年10月29日葬儀に参列する際に知っておきたい服装や香典のマナーを詳しく解説 葬儀2024年10月28日葬儀社選びのポイントは?サービスや費用について詳しく解説
葬儀2024年10月28日葬儀社選びのポイントは?サービスや費用について詳しく解説