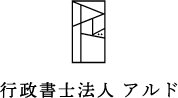突然の別れは、ご家族にとって大きな出来事です。この状況下で、何から手をつければ良いのか戸惑う方も多いでしょう。本記事では、死亡確認から葬儀の手続き、費用まで、葬儀に関する情報を詳しく解説します。ご遺族の皆様が少しでも安心して、故人様を送り出すお手伝いができれば幸いです。
目次-Contents-
死亡を確認したら

突然の別れは、ご本人様だけでなくご家族の方々にとっても大きなショックです。ご心からお見舞い申し上げます。この状況下で、何から手をつければ良いのか、戸惑う方も多いでしょう。
ここでは、ご逝去された後の死亡確認方法や病院での手続きについて、ご説明します。
死亡の確認
まずはじめに、医師による死亡の確認が必要です。一般的には、以下のいずれかの方法で行われます。
・病院で亡くなった場合:担当医が死亡診断書を作成します。
・自宅で亡くなった場合
かかりつけ医がいる場合…かかりつけ医に連絡し、医師に来てもらい死亡診断書を作成してもらいます。
かかりつけ医がいない場合…119番に連絡し、医師の指示に従い、最寄りの病院で死亡診断書を作成してもらいます。
病院での手続き
死亡診断書を受け取ったら、以下の手続きを行います。
- 葬儀社の選定:死亡診断書を参考に、複数の葬儀社に見積もりを依頼し、比較検討します。
- ご遺体の搬送:葬儀社にご遺体の搬送を依頼します。
- 死亡届の提出:死亡診断書と必要な書類を持って、役所に死亡届を提出します。
- 火葬許可証の申請:死亡届受理後、火葬許可証を申請します。
その他の手続き
- 銀行口座の解約:死亡届と印鑑証明書を持って、銀行で手続きを行います。
- 保険金の請求:各保険会社に死亡診断書などを提出して、保険金請求の手続きを行います。
- 公共料金の停止:電気、ガス、水道などの公共料金の支払いを停止する手続きを行います。
注意点
- 死亡診断書は大切に保管:死亡診断書は、相続手続きなど、様々な場面で必要となるため、大切に保管しましょう。
- 手続きの期限:各手続きには期限が定められている場合がありますので、早めに手続きを進めることをおすすめします。
- 専門家の相談:手続きが複雑な場合や、何か分からないことがあれば、葬儀社や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
通夜・葬儀の打ち合わせ

通夜や葬儀の手続きは初めての方にとっては、複雑に感じるかもしれません。しかし、葬儀社との打ち合わせは、スムーズな葬儀進行のためにも非常に重要です。
葬儀社との打ち合わせで決めること
| 葬儀の種類 | 葬儀の種類: 家族葬、一般葬、社葬など、どのような形式で行うか |
| 日程 | 通夜・告別式の日程、火葬の日程など |
| 場所 | 式場、火葬場など |
| 費用 | 葬儀全体の費用、内訳 |
| 宗教 | 仏教、神道、キリスト教など |
| 祭壇 | 祭壇のデザインや飾り付け |
| 参列者 | 予想される参列者数 |
| 返礼品 | 香典返しなど |
| その他 | 音楽、お花、料理など |
打ち合わせのポイント
- ・葬儀社の選び方:複数の葬儀社から見積もりを取り、比較検討することが大切です。
- ・費用:費用は葬儀の内容によって大きく異なります。事前に予算を決めておくと、スムーズに打ち合わせを進めることができます。
- ・疑問点は遠慮なく質問:わからないことは何でも質問し、納得のいくまで説明を受けるようにしましょう。
- ・冷静に判断:感情的にならず、冷静に判断することが大切です。
打ち合わせの進め方
- 葬儀社を決める:複数の葬儀社に見積もりを依頼し、比較検討します。
- 打ち合わせ日時を決める:葬儀社と打ち合わせの日時を決めます。
- 打ち合わせに持っていくもの:死亡診断書、故人の写真、印鑑など持ち物を確認しましょう。
- 打ち合わせ内容を確認:打ち合わせ内容をまとめた資料をもらって、よく確認しましょう。
葬儀の準備

葬儀の手続き、どこから始めたらいいの?どんな準備が必要なの?そんな疑問をお持ちの方に、葬儀の準備について詳しくご紹介します。
通夜
通夜の準備
通夜の準備は、葬儀社に依頼するのが一般的です。主な準備としては、以下のものが挙げられます。
- 会場の準備:通夜式を行う場所の設営(会場の飾り付け、祭壇の設置など)
- 飲食の準備:通夜振る舞い(軽食や飲み物)の準備
- 返礼品の準備:香典返しなどの準備
- 仏具の準備:仏壇、位牌、線香など
参列者のマナー
通夜に参列する際には、以下のマナーを守りましょう。
- 服装:喪服を着用します。
- 言葉遣い・静かに、落ち着いたトーンで話しましょう。
- 行動・携帯電話はマナーモードに、飲食は控えるなど、周囲に配慮しましょう。
- 香典:香典を持参し、受付で渡します。
- 数珠・仏式の場合は数珠を持参するのが一般的です。
告別式
告別式の進行
告別式の進行は、宗教や地域によって異なりますが、一般的には以下の流れで行われます。
- 開式:僧侶による読経が始まります。
- 焼香:参列者が順番に焼香を行い、故人に最後の別れを告げます。
- 献花:献花台に花を手向けます。
- 弔辞:故人の親しい方々から弔辞が述べられます。
- 閉式:僧侶による読経で締めくくり、出棺となります。
火葬
火葬の手順
火葬は、告別式の後に行われることが一般的です。火葬の手順は、地域や火葬場の設備によって多少異なる場合がありますが、一般的な流れは以下の通りです。
- 出棺:告別式の後、お棺を霊柩車に乗せ、火葬場に向かいます。
- 火葬場到着:火葬場に到着後、火葬許可証を提出します。
- 納めの式:火葬炉の前で、故人との最後の別れを告げる儀式を行います。僧侶による読経や焼香などが行われます。
- 火葬:お棺を火葬炉に納め、火葬が始まります。
- 収骨:火葬が終了した後、骨壺に収骨を行います。
火葬への立ち合い
火葬への立ち会いについては、遺族の意向によって異なります。立ち会う場合は、納めの式に参列し、火葬炉にお別れを告げることができます。
- 立ち会うメリット: 故人との最後の別れをしっかりと行うことができる、心の整理がつきやすいなど
- 立ち会わないメリット: 辛い場面を見なくて済む、精神的な負担を軽減できるなど
注意点
- 服装:火葬場内は冷房が効いている場合が多いので、薄手の羽織物があると便利です。
- 持ち物:ハンカチ、ティッシュなどを持参しましょう。
- マナー:静かに、落ち着いた態度で参列しましょう。
忌明けについて
忌明けとは、故人が亡くなってから一定の期間が経ち、喪に服す期間が終わることを指します。一般的には、四十九日が忌明けとされています。
四十九日
四十九日は、故人の霊が極楽浄土へ旅立つと考えられている日です。この日に、親族や親しい人を集めて法要を行い、故人を偲び、冥福を祈ります。四十九日以降は、喪服を喪服ではないものに替えることができ、日常生活に少しずつ戻っていくことができます。
一周忌
一周忌は、故人が亡くなってから一年後に行われる法要です。四十九日よりも大規模に行われることが多く、故人の冥福を祈り、一年間の感謝の気持ちを込めて行われます。
忌明けの過ごし方
忌明けの過ごし方は、宗派や地域、家族の考え方によって異なりますが、一般的には以下のようになります。
- 法要の準備:四十九日法要では、僧侶の手配、会場の予約、供物の手配など、様々な準備が必要です。
- 香典返し:四十九日法要の後に、香典をいただいた方々へのお礼として、香典返しを行います。
- 遺品の整理:故人の遺品を整理し、形見分けをする場合もあります。
- 墓参り:四十九日法要の後、墓参りを行い、故人に報告をします。
- 生活の再開:四十九日以降は、徐々に日常生活に戻っていきます。
忌中と忌明け
四十九日までを「忌中」といい、この期間は結婚式や旅行など、お祝い事や外出を控えることが一般的です。四十九日を過ぎると忌明けとなり、これらの制限が解除されます。
葬儀にかかる費用

葬儀の費用は、場合によって大きく異なり、具体的な金額が分かりづらいものです。家族葬、一般葬、直葬など、葬儀の種類によっても費用は変わってきます。ここでは、葬儀費用の相場や、費用の内訳、費用を抑えるためのポイントなどについて解説します。
葬儀費用内訳について
葬儀費用は、葬儀の種類や規模、地域によって大きく異なりますが、一般的に以下の項目で構成されています。
葬儀場使用料
- 式場使用料:通夜、告別式、親族控室などの使用料
- 控室使用料:親族や参列者が休憩する部屋の利用料
- 設備使用料:音響設備、照明設備などの使用料
棺
- 棺の種類:木製のシンプルなものから、装飾が施されたものまで、様々な種類があります。
- サイズ:故人の体型に合わせて選びます。
- 素材:木材、金属など、様々な素材があります。
お供え物
- 僧侶への御布施:読経や法要をしていただくための費用
- 霊柩車費用:故人の遺体を火葬場へ運ぶための費用
- 火葬場使用料:火葬を行うための費用
- 飲食費:通夜振る舞い、精進落としなどの費用
- 返礼品:香典返しなどの費用
- 印刷物:式次第、席次表、案内状などの費用
- 遺影写真:故人の写真を遺影に加工する費用
費用の相場
葬儀費用は、地域や宗教、葬儀の規模など、さまざまな要素によって大きく変動します。ここでは、これらの要素がどのように費用に影響を与えるか、簡単にご説明します。
1. 地域による違い
- 都市部と地方:一般的に、都市部の方が物価が高いため、葬儀費用も高くなる傾向があります。特に、大都市圏では、葬儀場や霊柩車の費用が高めに設定されているケースが多いです。
- 地域ごとの慣習:各地域には独自の葬儀風習があり、それに伴う費用も異なります。例えば、ある地域では、通夜振る舞いが盛んに行われるため、飲食費が高くなることがあります。
2. 宗教による違い
- 仏教:日本で最も一般的な宗教であり、宗派によっても費用が異なります。真宗では、簡素な葬儀を行うことが多く、費用を抑えられる傾向があります。
- キリスト教:カトリックやプロテスタントなど、宗派によって儀式の内容や費用が異なります。
- 神道:神道式の場合、神職への御礼や神具の費用などが発生します。
3. 規模による違い
- 家族葬:親族中心の小規模な葬儀で、一般葬に比べて費用を抑えられることが多いです。
- 一般葬:親族だけでなく、友人や会社関係者など、多くの人を招待する葬儀です。規模が大きくなるため、費用も高くなります。
- 直葬:通夜や告別式を行わず、火葬のみを行う簡素な葬儀で、費用を大幅に抑えることができます。
4. 葬儀の内容による違い
- 祭壇: 生花や装飾の有無によって費用が異なります。
- 棺: 素材や装飾によって費用が異なります。
- 飲食: 通夜振る舞い、精進落としなどのメニューや規模によって費用が異なります。
- 返礼品: 香典返しなど、返礼品の品物や数量によって費用が異なります。
5. 葬儀社のサービスによる違い
- 付帯サービス:僧侶の手配、返礼品の選択、施設の手配など、葬儀社が提供するサービスによって費用が異なります。
- プラン:各葬儀社では、様々な葬儀プランを用意しており、プランの内容によって費用が異なります。
葬儀費用の相場
葬儀費用の相場は、上記のような要素によって大きく変動するため、一概にいくらとは言えません。しかし、一般的な葬儀の場合、100万円~200万円程度が相場と言われています。
費用を抑えるためには
葬儀費用を抑えたい場合は、以下の点に注意すると良いでしょう。
- 葬儀の種類:家族葬など、小規模な葬儀を選ぶ
- 不要なサービスを見直す:通夜振る舞いなどを省く
- 比較検討する:複数の葬儀社から見積もりを取り、比較検討する
- DIY:式次第や席次表などを手作りする
まとめ
葬儀の手続きは、初めての方にとっては複雑に感じるかもしれません。しかし、この記事で紹介した情報を参考に、一つずつ丁寧に対応することで、スムーズに葬儀を進めることができます。
もし、何かご不明な点があれば、葬儀社や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
監修

- 行政書士・弁護士
-
法的準備は、安心した生活の基盤になりますし、将来の手続負担の軽減にもつながります。手続きを知り、備えることで、自分らしく生きるきっかけになればと思い、生前のサポートを充実させることを大切にしています。
遺言書の作成や、死後の手続支援(死後事務委任)、不動産に関する手続きなどについて、相続専門の行政書士法人として、幅広く情報提供をさせていただき、一人一人の生活に合った選択肢を一緒に考えてきます。
最新の投稿
 永代供養2024年12月28日永代供養墓とは?種類や必要性、そして歴史・選び方まで徹底解説!
永代供養2024年12月28日永代供養墓とは?種類や必要性、そして歴史・選び方まで徹底解説! 葬儀2024年12月26日葬儀の流れを徹底解説。事前準備や基礎知識、葬儀社選び、葬儀後の手続きを紹介
葬儀2024年12月26日葬儀の流れを徹底解説。事前準備や基礎知識、葬儀社選び、葬儀後の手続きを紹介 お部屋の片付け・遺品整理2024年10月29日葬儀に参列する際に知っておきたい服装や香典のマナーを詳しく解説
お部屋の片付け・遺品整理2024年10月29日葬儀に参列する際に知っておきたい服装や香典のマナーを詳しく解説 葬儀2024年10月28日葬儀社選びのポイントは?サービスや費用について詳しく解説
葬儀2024年10月28日葬儀社選びのポイントは?サービスや費用について詳しく解説