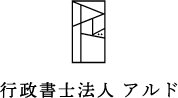葬儀は、故人を偲び、遺族を慰める大切な場です。しかし、宗教や地域によって、葬儀の形式やマナーが異なるため、初めて参列する方は特に戸惑ってしまうかもしれません。この記事では、葬儀に参列する際に必ず知っておきたい、服装や香典のマナーについて解説します。これらの知識を事前に身につけることで、慌てることなく、故人へ最後の別れを告げることができます。
目次-Contents-
葬儀に参列する際の心構え

葬儀は、故人を偲び、ご遺族の悲しみを分かち合い、慰める大切な場です。参列する際には、以下の点に気をつけ、静かにそして慎んでご遺族をサポートしましょう。
心構えのポイント
携帯電話はマナーモードに: 携帯電話はマナーモードに、もしくは電源を切るようにしましょう。着信音が鳴ったり、振動が伝わったりすると、周囲に不快感を与えてしまいます。
故人への感謝と、ご遺族への弔いの気持ちを持つ: 故人の生前のことを思い出し、感謝の気持ちを持ちましょう。また、悲しみに暮れるご遺族に温かい言葉をかけてあげることが大切です。
静粛を保つ: 葬儀は厳粛な場です。大きな声での会話や、私語は控え、静かに過ごしましょう。
葬儀に参列する際の服装のマナー|男女別に詳しく解説

日本の葬儀は、故人を偲び、遺族を慰める大切な場です。そのため、参列する際の服装には、故人への敬意と遺族への弔意を表すという重要な意味合いがあります。ここでは、男女別の服装マナーについて詳しく解説します。
男性の服装
- スーツ: 黒色のスーツが一般的です。ダブルブレスト、シングルブレストどちらでも構いません。
- ワイシャツ: 白のワイシャツを着用します。襟はレギュラーカラーかワイドカラーが一般的で、カジュアルな印象を与えるボタンダウンシャツは避けましょう。
- ネクタイ: 黒色の無地のネクタイを着用します。
- 靴: 黒色の革靴を着用します。
- その他:
- 靴下は黒色。
- ベルトは黒色でシンプルなデザインのもの。
- 腕時計は、ビジネスシーンで着用するようなシンプルなものが無難です。
- 結婚指輪以外のアクセサリーは避けるのが一般的です。
女性の服装
- ブラックフォーマル: 黒色のワンピースやアンサンブルが一般的です。
- 素材: 光沢のある素材や透け感のある素材は避け、落ち着いた素材を選びましょう。
- アクセサリー: 結婚指輪以外のアクセサリーは控えめにしましょう。パールネックレスなどは、落ち着いた印象を与えるのでおすすめです。
- 靴: 黒色のパンプスを着用します。
- ストッキング: 黒色のストッキングを着用します。
- 髪型: 髪はアップスタイルか、まとめ髪にするのが一般的です。派手な髪色は避け、自然な色合いにしましょう。
- 化粧: 薄めのメイクにしましょう。口紅は控えめな色を選び、アイシャドウも控えめな色を選びましょう。
共通して注意すべき点
- 華美な服装は避ける: 派手な色や柄、露出の多い服装は避けましょう。
- 香りは控えめに: 香水などの香りは控えめにするか、つけない方が良いでしょう。
- 持ち物: 数珠、ハンカチ、袱紗などを用意しておくと便利です。
その他
- 季節: 夏場など、暑い時期には、素材や服装に工夫を凝らすことも必要です。
- 宗教: 宗教によっては、服装に多少の違いがある場合があるので注意しましょう。
- 故人との関係性: 故人との関係性によっても、服装に違いがある場合があります。
まとめ
葬儀の服装は、故人への敬意と遺族への弔意を表す大切なものです。上記を参考に、失礼のない服装で参列しましょう。ご不明な点がある場合は、葬儀社に問い合わせるなどして、事前に確認しておくことをおすすめします。
また、近年では、宗教や宗派によらず、故人を偲ぶ気持ちを表すことが重視されるようになってきています。そのため、厳格な服装マナーにこだわるよりも、故人への感謝の気持ちを持って参列することが大切です。
香典のマナー|金額、表書き、包み方など、知っておきたいこと
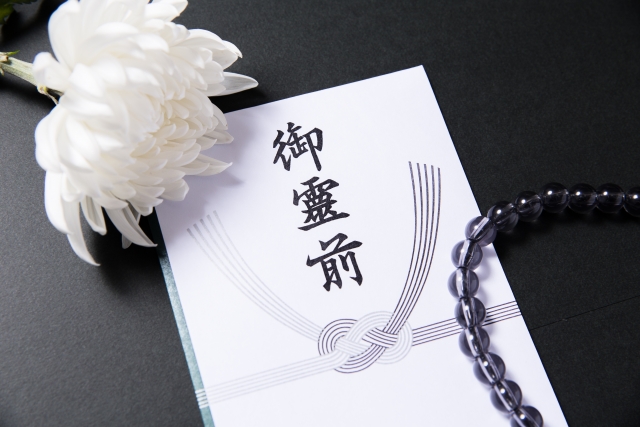
葬儀に参列する際、香典は故人への供養と遺族への弔いの気持ちを表す大切なものです。しかし、金額や表書き、包み方など、様々なマナーがあり、戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。この記事では、香典に関する基本的なマナーを解説します。
香典の金額
香典の金額は、故人との関係性や経済状況などを考慮して決めるのが一般的です。
- 故人が親族の場合の一般的な金額の目安:
- 両親:5万円~10万円
- 兄弟・姉妹:3万円~5万円
- 祖父母:1万円~5万円
- 叔父・叔母:1万円~3万円
- 故人が親族でない場合の一般的な金額の目安:
- 友人・知人:5千円~1万円
- 先生・近所の方:3千円~1万円
- 職場の同僚など:5千円~1万円
- 金額の決まりごと:
- 奇数で表す:偶数は割り切れることから、縁起が悪いとされています。
- 新札を折らずに入れる:新しいお札を折らずに、丁寧に包みましょう。
表書きの書き方
表書きは、香典袋の表に書く言葉で、故人への弔いの気持ちを表します。
- 霊名: 故人の正式な霊名を書きます。
- 自分の名前: フルネームで書きましょう。
- 続柄: 故人との続柄を書きましょう(例:弟の山田太郎、会社員の鈴木花子など)。
- 連名の場合は: 代表者の名前を書き、「一同」や「外一同」と加えます。
| 関係性 | 表書き |
| 故人の息子 | 御仏前 山田太郎 |
| 故人の友人 | 御霊前 鈴木花子 |
| 会社の同僚一同 | 御仏前 営業部一同 代表 山田太郎 |
包み方
香典は、正方形の白いふくさに包んで持参するのが一般的です。
- ふくさの選び方:
- 慶弔用のふくさを選びましょう。
- 素材は、絹やちりめんが一般的です。
- 包み方:
- 香典袋をふくさの真ん中に置き、対角線上に折りたたんで包みます。
水引の種類
水引の種類は、蝶結びと結び切りの2種類があります。
- 蝶結び: 繰り返すことが可能なことから、何度でも繰り返すお祝い事(結婚など)に用いられます。
- 結び切り: 繰り返すことができないことから、繰り返さないことを願う弔事に用いられます。
香典には、結び切りの水引を使用します。
香典を持参するタイミング
香典は、受付で記帳をした後、受付に渡すのが一般的です。
- 受付で渡す場合:
- 受付で名前と住所を記入し、香典を渡します。
- 一言、お悔やみの言葉を添えると丁寧です。
- ご遺族に直接手渡す場合:
- ご遺族に直接手渡す場合は、ふくさに包んだ状態で、両手で差し出し、深々と頭を下げてお悔やみの言葉を述べます。
香典は、故人への感謝の気持ちと、ご遺族への弔いの気持ちを表す大切なものです。この記事で紹介したマナーを参考に、失礼のないように参列しましょう。
焼香のマナーと作法

焼香は、故人に最後の別れを告げ、冥福を祈るための仏教の儀式です。焼香の作法は宗派によって多少異なりますが、基本的な流れは共通しています。
焼香の作法
- 順番: 一般的に、僧侶、親族、参列者の順に焼香を行います。
- 焼香台へ: 焼香台の前まで進み、遺影に向かって一礼します。
- 合掌: 合掌し、静かに深呼吸をします。
- 香をあげる: 右手で抹香をつまみ、香炉に向かって静かに香をあげます。香を立てすぎないように注意しましょう。
- 火を消す: 香が燃え尽きる前に、香炉の縁で火を消します。
- 再度合掌: 合掌し、静かに深呼吸をします。
- 一礼: 遺影に向かって一礼し、焼香台から離れます。
注意点
- 香を立てすぎない: 香を立てすぎると、煙が目に染みたり、火事になる恐れがあります。
- 火傷に注意: 香炉が熱くなっているので、火傷に注意しましょう。
- 静粛を保つ: 焼香中は静かにし、他の参列者に迷惑をかけないようにしましょう。
- 宗派による違い: 宗派によって、焼香の回数や作法が異なる場合があります。事前に確認しておくと良いでしょう。
その他
- 数珠: 数珠を持っている場合は、焼香の際に左手にかけるのが一般的です。
- 服装: 焼香の際は、正座をすることが多いので、動きやすい服装で参列しましょう。
- 焼香台の位置: 焼香台の位置は、宗派や会場によって異なります。
- 焼香の時間: 焼香の時間は、宗派や会場によって異なります。
焼香は、故人への感謝の気持ちを込めて行う大切な儀式です。 上記の作法を参考に、静かにそして慎んで焼香を行いましょう。もし、ご不明な点がある場合は、葬儀社にご確認ください。
葬儀におけるその他のマナー
数珠
数珠は、仏教徒が念仏を唱える際に使用する仏具ですが、葬儀の場では故人を偲ぶための道具としても用いられます。
- 数珠を持つ意味:
- 仏さまとのつながりを意識し、心を落ち着かせる。
- 故人を偲び、冥福を祈る。
- 使い方:
- 焼香の際に、左手首にかける。
- 宗派によって、数珠の持ち方や数え方が異なるため、事前に確認しておくとよい。
弔辞
弔辞は、故人を悼む言葉を述べるものです。
- 弔辞を読む際の注意点:
- 故人との関係性やエピソードを簡潔に述べる。
- 故人の人となりや功績をたたえる。
- 忌み言葉を避ける。
- 感情的になりすぎず、落ち着いたトーンで話す。
- 時間に注意し、長くなりすぎないようにする。
返礼品
返礼品は、香典に対するお礼として、後日、参列者に送られます。
- 返礼品の意味:
- 香典に対する感謝の気持ちを表す。
- 故人を偲んでもらうきっかけとなる。
- マナー:
- 香典の金額に見合った品物を贈る。
- 故人の好きだったものや、故人の思い出の品をモチーフにしたものが一般的。
- 手紙を添えて、感謝の気持ちを伝える。
忌み言葉
葬儀の場では、縁起が悪いとされる忌み言葉を避けることが大切です。
- 例:
- 別れる、切る、終わる
- 返す、繰り返す
- 病気、苦しむ
- 切れる、壊れる
- 暗い、黒い
葬儀は、故人を偲び、遺族を慰める大切な場です。数珠、弔辞、返礼品、忌み言葉など、様々なマナーを理解し、故人への敬意と遺族への弔意を表しましょう。
葬儀に関するよくある質問と回答
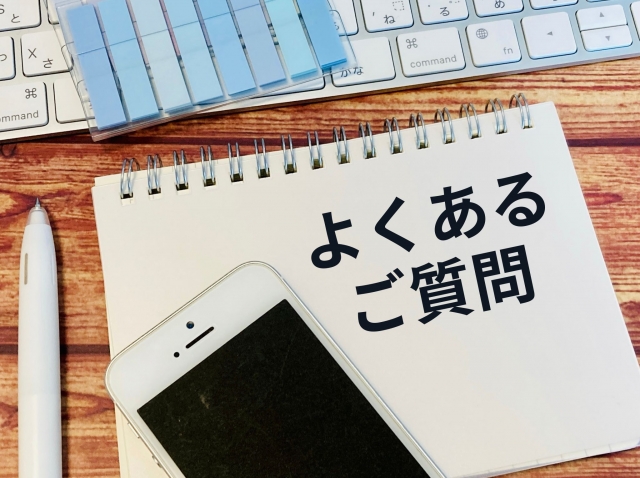
葬儀に参列する際、様々な疑問が浮かぶ方もいらっしゃるでしょう。ここでは、葬儀に関するよくある質問とその回答をまとめました。
葬儀に参列できない場合の対応
葬儀に参列できない場合、以下のような対応が考えられます。
- 弔電: 弔電を弔問の代わりとすることが一般的です。故人の冥福を祈り、遺族を慰める言葉を伝えましょう。
- 供花: 生花や供物などを贈ることもできます。
- 香典: 後日、香典を郵送することも可能です。
- お悔やみの手紙: 手紙で故人への弔意と、遺族への慰めの言葉を伝えましょう。
忌明けとは?
忌明けとは、故人の霊が仏様になるとされる期間のことです。一般的には、故人が亡くなってから49日目に行われる法要を指します。忌明け以降は、喪服を着用する必要がなくなり、通常の生活に戻ることが一般的です。
四十九日とは?
四十九日とは、故人が亡くなってから49日目のことです。仏教では、亡くなった人の魂が49日で極楽浄土に生まれ変わると考えられているため、この日に追善供養を行います。
その他、よくある質問
- 香典の金額はどのくらいが適切ですか? 故人との関係性や経済状況によって異なりますが、一般的には、親族は3万円~、親しい友人なら1万円~など、故人との関係性によって金額が変わってきます。
- 香典の表書きはどう書けばいいですか? 故人の霊名と、自分の名前、続柄を書きましょう。例えば、「御仏前 山田太郎」のように書きます。
- 数珠は持参した方がいいですか? 数珠を持っている場合は、持参すると良いでしょう。
- 服装はどんなものが良いですか? 黒色の喪服が一般的です。
- 焼香の仕方は? 焼香台の前で一礼し、合掌して香をあげ、火を消した後、再度一礼します。
- 忌み言葉は? 「別れる」「切る」「終わる」など、ネガティブな言葉は避けましょう。
まとめ
葬儀は、故人を偲び、ご遺族を慰める大切な場です。この記事では、葬儀に参列する際の服装、香典、焼香など、基本的なマナーについて解説しました。
服装は、故人への敬意と遺族への弔意を示す重要な要素です。黒色の喪服を着用し、華美な装飾や派手な色は避けましょう。
香典は、故人への供養と遺族への弔いの気持ちを表すものです。金額や表書き、包み方など、決まったマナーがあります。
焼香は、故人に最後の別れを告げる儀式です。静かに、そして慎んで行いましょう。
その他にも、数珠、弔辞、返礼品など、葬儀には様々なマナーがあります。これらのマナーを理解し、故人への感謝の気持ちと、遺族への弔いの気持ちを持って参列することが大切です。
葬儀のマナーは、宗派や地域によって異なる場合があります。 不安な場合は、葬儀社に問い合わせるなどして、事前に確認しておくと安心です。
監修

- 行政書士・弁護士
-
法的準備は、安心した生活の基盤になりますし、将来の手続負担の軽減にもつながります。手続きを知り、備えることで、自分らしく生きるきっかけになればと思い、生前のサポートを充実させることを大切にしています。
遺言書の作成や、死後の手続支援(死後事務委任)、不動産に関する手続きなどについて、相続専門の行政書士法人として、幅広く情報提供をさせていただき、一人一人の生活に合った選択肢を一緒に考えてきます。
最新の投稿
 永代供養2024年12月28日永代供養墓とは?種類や必要性、そして歴史・選び方まで徹底解説!
永代供養2024年12月28日永代供養墓とは?種類や必要性、そして歴史・選び方まで徹底解説! 葬儀2024年12月26日葬儀の流れを徹底解説。事前準備や基礎知識、葬儀社選び、葬儀後の手続きを紹介
葬儀2024年12月26日葬儀の流れを徹底解説。事前準備や基礎知識、葬儀社選び、葬儀後の手続きを紹介 お部屋の片付け・遺品整理2024年10月29日葬儀に参列する際に知っておきたい服装や香典のマナーを詳しく解説
お部屋の片付け・遺品整理2024年10月29日葬儀に参列する際に知っておきたい服装や香典のマナーを詳しく解説 葬儀2024年10月28日葬儀社選びのポイントは?サービスや費用について詳しく解説
葬儀2024年10月28日葬儀社選びのポイントは?サービスや費用について詳しく解説