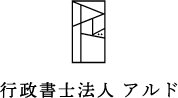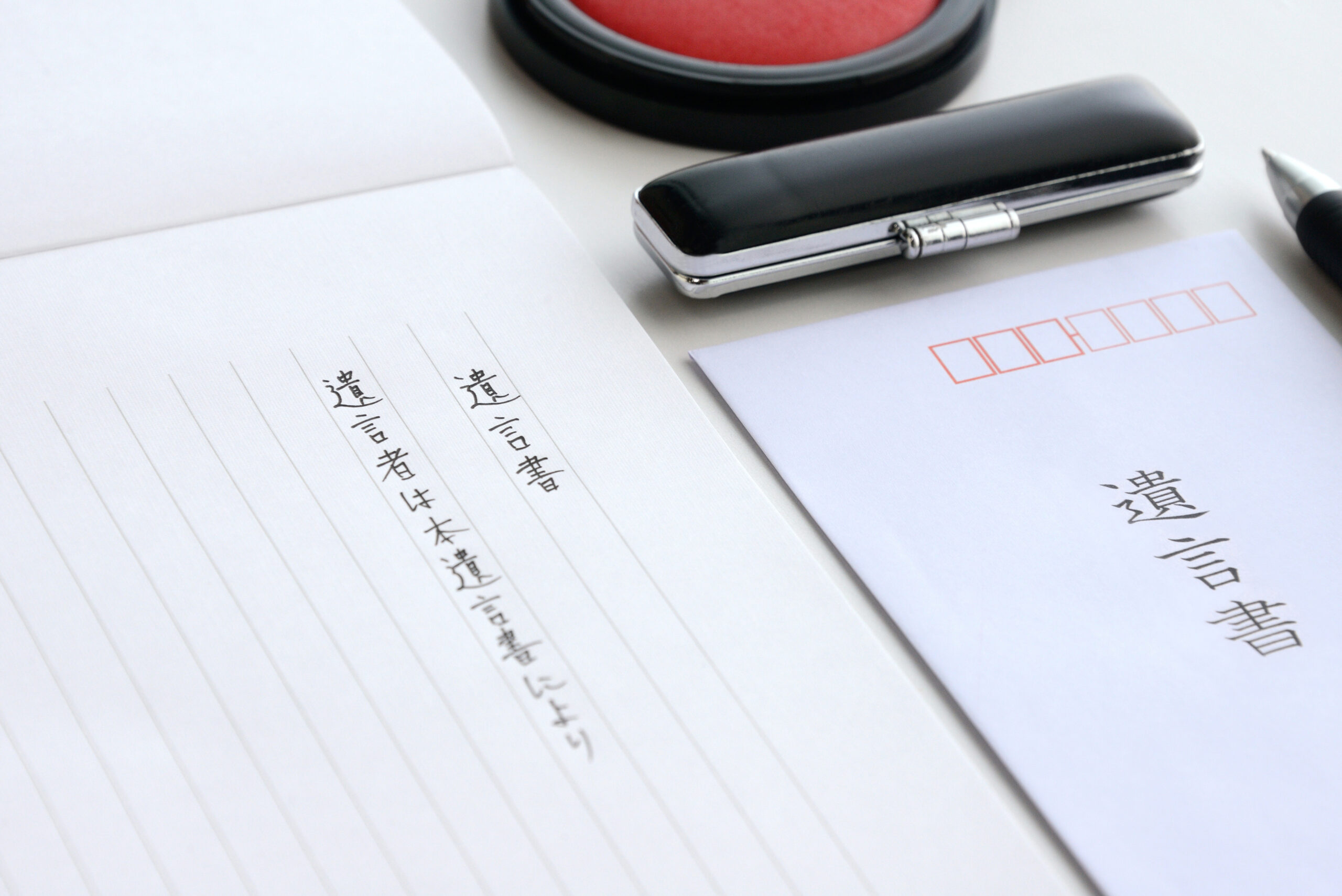目次-Contents-
遺言書とは?
遺言書(ゆいごんしょ)とは個人が死亡した後に遺産分割や財産の処理に関する指示を残す法的な文書で、個人の最終的な意志や希望を表明し、財産の相続や配分に関する指示を明確にするために使用されます。遺言書を作成することで、個人が自身の財産や資産に関してどのような希望や要望を持っているかを法的に確認することができる重要な文書です。
遺言書には、遺言者(遺産を残す人)や相続人(遺産を受け継ぐ人)、遺産の分割方法、特定の遺産項目や財産に関する具体的な指示、そして遺言書の作成日などが含まれます。
また、遺言書は個人の自由な意思に基づいて作成されるため、その内容は多岐にわたります。財産の分配だけでなく、子供(未成年)の後見人の指定、葬儀や埋葬に関する希望、慈善団体への寄付なども含まれることがあります。遺言書は、ご自身の財産の活用の手段といえますし、遺産分割を円滑に進める手段でもあります。遺産分割での親族間のトラブルを未然に防ぎ、ご家族の負担を軽減する点でも重要なものです。
遺言書には種類がある?
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。それぞれの特徴をチェックしてみましょう。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で全文、指名、日付を自筆し押印 | 本人と承認2名で公証役場や行き、本人から遺言内容を話し、公証人が記述 | 遺言に署名、押印し、封印して公証役場で証明をしてもらう |
| 証人 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 保管 | 被相続人が保管 | 公証役場で保管 | 被相続人が保管 |
| 検認手続き | 必要 | 不要 | 不要 |
| 費用 | 0円(法務省保管の場合は別途3900円) | 16,000円~(財産に応じて加算) | ・公証人手数料:11,000円 ・証人手配料:1名あたり5,000円~10,000円程度 ・専門家報酬(専門家に相談する場合):事務所毎に異なる |
| メリット | ・手軽に作成が可能 | ・法的に有効な遺言書を作成できる ・紛失リスクがない |
・遺言書が本物であることを証明できる ・遺言内容を秘密にしておくことができる |
| デメリット | ・無効になるリスク ・紛失のリスク |
・時間と費用がかかる ・遺言内容を秘密にできない |
・費用がかかる ・無効になるリスク ・紛失のリスク |
遺言書でできること
① 特定の相続人に多くの遺産を取得させる
遺言書は、遺産分配において特定の相続人に重点を置くために使用されます。遺言者は、希望する相続人に特定の財産や資産を割り当て、法的な手続きを経てこれを確定させることができます。これにより、遺産分配が遺言者の意向に従って行われることが保証されます。
② 内縁の妻や孫など相続人でない人に遺産を遺贈する
遺言書は、法定相続人以外の人に贈与を行う手段としても機能します。内縁の妻や孫、友人など、法的な相続人でない人に対しても、特定の財産や遺産を遺贈することができます。これにより、遺言者の希望に基づいた相続が実現します。
③ 遺産を寄付する
遺言書を使用して、遺産を慈善団体や特定の慈善事業等に寄付したり、基金を造成することができます。これにより、遺言者は、ご自身の財産を、社会のために活用することができます。
④ 子どもを認知する
遺言書は、法的に子どもを認知する手段としても使用されます。子どもが法的な手続きを経ずに遺産を相続するためには、遺言書において子どもを明示的に認知することが重要です。
⑤ 相続人の排除
遺言書では、法定相続人の中から特定の相続人を除外することも可能です。これにより、特定の人に対して相続権を剥奪し、他の相続人による遺産の分配を円滑に進めることができます。
⑥ 遺産分割方法の指定や禁止
遺言書には、遺産分割の具体的な方法や、あるいは分割を禁止する条件を明示することができます。これにより、遺言者の意向に合った遺産分配が実現されます。
⑦ 後見人の指定
遺言書は、未成年の子どもや特定の相続人に対する後見人を指定する手段としても利用できます。後見人は、法的な責任を負って未成年者や特定の相続人の利益を保護する役割を果たします。
⑧ 遺言執行者の指定
遺言書には、遺言者の意向を実現するために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、遺産分配の手続きを管理し、遺言者の意向を遵守します。
⑨ 生前贈与した場合の遺産の処理方法
遺言書は、遺産の一部が事前に贈与された場合において、その処理方法を指定できます。これにより、遺言者が生前に贈与を行った場合でも、残された遺産が公正かつ合理的な方法で分割されることが確認されます。
⑩ 生命保険の受取人の変更
遺言書には、生命保険の受取人を変更するための指示を含めることができます。これにより、生命保険の受取人を法定相続人以外の人に指定することが可能です。
遺言書の効力はいつからいつまで?
遺言書の効力は、遺言者が死亡した時点から発生します。具体的な時期は、遺言書の法的手続きが完了し、遺言書が有効と認められた日です。以下の一般的な流れを確認してみてください。
①作成と署名
遺言者が遺言書を作成し、遺言書に署名します。遺言書は公正証書や自筆証書など、法定の形式に従っている必要があります。
②法的手続き
遺言書は、法的な手続きを経て公証役場で公正証書遺言書として認証されるか、あるいは自筆証書遺言書として法的な効力が認められる必要があります。
③死亡
遺言者が死亡すると、その時点から遺言書が有効になります。
④遺言執行
遺言者の死亡後、遺言書の内容に基づいて遺産分割が行われます。遺言執行者や法定相続人が法的手続きを進め、遺産分割が実現します。
遺言書の効力は、死亡した遺言者の遺産分割に関する指示が実行されるまで続きます。ただし、一般的に遺言書には期限が設けられていないため、法的な手続きが進まない限り、その効力は続きます。遺言書が有効である限り、その内容が尊重され、遺産分割が遺言者の意図に基づいて行われます。
遺言書が複数ある場合、効力があるのは?
複数の遺言書が存在する場合、一般的には最後に作成された遺言書が効力を持ちます。これを「最後の遺言の原則(Lapse of Prior Wills)」と呼びます。最後に作成された遺言書が、それ以前の遺言書を置き換えるものとされます。
以下の一般的なケースを確認してみましょう。
①最後の遺言書が有効
複数の遺言書が存在する場合、最後に作成された遺言書が法的な効力を持ちます。このため、遺言者が複数の遺言書を作成した場合、最後の意思表示が尊重されます。
②矛盾がある場合
複数の遺言書に矛盾がある場合、法的な解釈や裁定が必要となることがあります。裁判所は、遺言者の真の意図を把握し、最も具体的で最後の遺言書を適用するよう努めます。
重要なのは、法的な手続きが適切に行われ、遺言書が法的に有効であるかどうかです。公正証書遺言書や自筆証書遺言書など、法的な要件を満たす形式で作成されているかがポイントとなります。それでも疑義が残る場合、裁判所が介入し、解釈や優先順位を確定することがあります。
遺言書を勝手に開封すると効力がなくなるの?
一般的に、遺言書は遺言者が死亡した後に裁判官が開封し内容を確認する法的手続き(検認)が必要です。遺言書は遺言者の最後の意思表示であり、プライバシーと尊重されるべきものです。
もし、勝手に開封してしまった場合でも、正式な遺言書であれば有効ですが、開封してしまった場合は申告をした上で検認の手続きを行う必要があります。
しかしながら、遺言書を相続人が勝手に開封することは法律違反に該当するため行政罰として5万円以下の罰金となる可能性があります。
遺言書の適切な書き方
遺言書を正確かつ法的に有効に作成するための基本的な手順を確認してみましょう。今回は3種類の遺言書の中で「自筆証書遺言」の書き方について解説します。
①全文自筆で書く
遺言書は全文を遺言者自身の直筆で書く必要があります。他人に代筆させないようにし、自分の意思が直接文書に表れるようにします。プリントやタイプでの作成は避け、手書きが望ましいです。
②日付を入れる
遺言書には作成日を明示的に書き込むことが大切です。作成日が明確になることで、最後に書かれた遺言書がどれであるかが識別されます。
③氏名を自筆で書き押印する
遺言者は自分の氏名を直筆で書き、署名または押印します。これにより、遺言者自身がその遺言書を作成したことが確認され、遺言書が本人の意思を反映していることが証明されます。
③訂正や加筆の場合は決められた方式を守る
もし遺言書に訂正や加筆が必要な場合、法的に認められる方法で行います。通常、訂正部分に対して直筆で署名し、訂正日を明記します。これにより、後からの変更が遺言者の本意であることが確認されます。
④書面で作成する
遺言書は書面で作成することが求められます。通常、紙に手書きで起草され、公正証書遺言書の場合は公証役場で作成されます。※電子的な形式や口頭での遺言は、法的に認められない可能性があるため、書面での作成が望ましい。
これらの手順を守ることで、遺言書が法的に有効であり、遺言者の最後の意思が正確に表現されることが期待されます。ただし、法的要件は地域によって異なるため、適切な法的助言を受けることが重要です。
遺言書を作成時に気を付けたい無効になってしまうケース
遺言書を作成する際には、特定の要件や法的な原則を遵守することが重要です。遺言書が無効になる可能性があるケースをご紹介します。
①証人の不足または不適格な証人
「公正証書遺言」「秘密証書遺言」には適格な証人が必要です。証人が足りない、または法的に認められない場合、遺言書は無効とされることがあります。適格な証人は、成人であり、精神的に健康であることが求められます。また、推定される相続人や財産をもらう受遺者とその配偶者、直系血族のほか、公証人の配偶者や四親等内の親族も証人になることができません。
②強制または詐欺の影響
遺言者が他者によって強制されたり、詐欺に巻き込まれたりして遺言を作成した場合、その遺言書は無効とされる可能性があります。
③遺言者の精神状態の不適切な影響
遺言者が精神的に不適切な状態である場合、その遺言書が無効とされることがあります。例えば、認知症や精神疾患により遺言者が意思決定能力を失っている場合などが該当します。
④自筆でない場合
「自筆証書遺言」は、全文が遺言者自身の手で直筆で書かれる必要があります。もし他人が代筆した場合、法的に無効とされる可能性があります。
⑤法定手続きの不遵守
各地域や法域には特定の法定手続きが存在します。これには、公正証書遺言書や証人の立ち会いが必要な場合があります。これらの手続きを遵守しないと、遺言書は無効とされる可能性があります。
⑥他の有効な遺言書が存在する場合
遺言者が複数の遺言書を作成した場合、最後の遺言書が通常優先されます。しかし、それ以前の遺言書がまだ有効である可能性もあるため、矛盾が生じることがあります。
これらは一般的なケースであり、具体的な法的要件は地域によって異なる場合があります。遺言書を作成する際には、地元の法律を確認し、適切な法的助言を受けることが重要です。
遺言書作成でトラブルを未然に防ぐための工夫
遺言書を作成する際に、トラブルを未然に防ぐために重要なポイントをチェックしてみましょう。
①遺留分を侵害しないようにする
遺留分は、法定相続分であり、遺言者が自由に分配できる範囲が制約されています。遺留分を侵害しないようにするために、相続人や法定相続分に関する法的な知識を確認し、公正かつ公平な分配を心掛けることが重要です。
②公正証書遺言を利用する
公正証書遺言書は、公証役場で作成されるもので、法的な効力が非常に高いです。この形式を利用することで、遺言の真正性が保証され、トラブルのリスクが軽減されます。公正証書遺言書を作成するには、公証役場での手続きが必要ですが、信頼性が向上します。
③弁護士や司法書士に相談する
弁護士や司法書士に相談することで、法的な専門知識を得ることができます。専門家のアドバイスを受けながら遺言書を作成することで、法的な問題を回避し、遺言の意図が明確になります。特に相続に関する複雑な事情がある場合、専門家の助言が不可欠です。
これらの工夫を組み合わせることで、遺言書作成においてトラブルの未然防止に寄与します。遺言書は個人の最終的な意思を反映するものであり、法的な手続きを正確かつ公正に行うことが大切です。
監修

- 行政書士・弁護士
-
法的準備は、安心した生活の基盤になりますし、将来の手続負担の軽減にもつながります。手続きを知り、備えることで、自分らしく生きるきっかけになればと思い、生前のサポートを充実させることを大切にしています。
遺言書の作成や、死後の手続支援(死後事務委任)、不動産に関する手続きなどについて、相続専門の行政書士法人として、幅広く情報提供をさせていただき、一人一人の生活に合った選択肢を一緒に考えてきます。
最新の投稿
 永代供養2024年12月28日永代供養墓とは?種類や必要性、そして歴史・選び方まで徹底解説!
永代供養2024年12月28日永代供養墓とは?種類や必要性、そして歴史・選び方まで徹底解説! 葬儀2024年12月26日葬儀の流れを徹底解説。事前準備や基礎知識、葬儀社選び、葬儀後の手続きを紹介
葬儀2024年12月26日葬儀の流れを徹底解説。事前準備や基礎知識、葬儀社選び、葬儀後の手続きを紹介 お部屋の片付け・遺品整理2024年10月29日葬儀に参列する際に知っておきたい服装や香典のマナーを詳しく解説
お部屋の片付け・遺品整理2024年10月29日葬儀に参列する際に知っておきたい服装や香典のマナーを詳しく解説 葬儀2024年10月28日葬儀社選びのポイントは?サービスや費用について詳しく解説
葬儀2024年10月28日葬儀社選びのポイントは?サービスや費用について詳しく解説