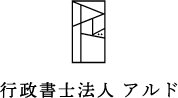最近では永代供養という言葉を耳にする機会が増えてきました。かつては一家にひとつ必要とされてきたお墓も現代では継承する人がいないなど管理することが難しくなってきています。そこで注目されているのが永代供養。ここでは、永代供養に関する疑問や費用相場、メリット、デメリットを徹底解説します。
目次-Contents-
永代供養とは?

永代供養とは、一定期間中に故人の遺骨を寺院や霊園などの供養施設に収め、供養を継続的に行ってもらうことを意味します。永代供養は、大きく分けると、家族ごとに埋葬する「個別型」と他の家の遺骨と一緒に埋葬される「合祀型」の2種類。永代供養は、子どもや親族にお墓を継承しないことを前提としている為、身寄りがないという方以外にも「子どもに負担をかけたくない」「お墓に費用をかけずに資産を子どもに残したい」と考える方に選ばれています。
永代供養にはどんな方法がある?全5種類を解説

永代供養にはいくつかの異なる種類が存在します。ここでは一般的な永代供養の方法5種類を紹介します。
・合祀型永代供養
合祀型永代供養は、最もスタンダードな方法で、骨壺を開け、複数の故人が一つの霊廟や供養スペースで供養される形態です。
・集合型永代供養
集合型永代供養は、骨壺はそのままで複数の霊廟や供養施設が一つの施設内に集まっている形態です。故人ごとに霊廟を選び、個別の供養を行います。
・墓石型永代供養
墓石型永代供養は、墓地の区画に墓石を置き、一般墓と永代供養がセットになっているお墓のことです。
・樹木葬型永代供養
樹木葬型永代供養は、故人の遺骨や遺灰が樹木の根元に埋葬される形態です。故人の霊は樹木によって供養されます。
・納骨堂型永代供養
納骨堂型永代供養は、納骨堂と呼ばれる施設を通じて行われ、故人の遺骨や遺灰が納骨堂に収められ、一定期間供養が続けられます。一定期間後には合祀されます。
永代供養の費用を種類別に解説

永代供養の費用は、選択した供養方法や施設によって異なります。ここでは、一般的な永代供養の費用について解説します。
・合祀型、集合型の永代供養でかかる費用
合祀型にかかる費用は3万円~30万円程です。費用に内訳は以下の3点
①永代供養料
②納骨料
③彫刻料
未来永劫供養してもらうために必要な永代供養料に加え、遺骨を納める際に必要な納骨料、墓誌に名前を刻む時にかかる彫刻料が必要になってきます。
まら、一定期間に個別供養してもらう場合は別途費用が発生します。
・墓石型永代供養でかかる費用
墓石型永代供養にかかる費用は30万円~200万円程です。
墓石の種類や広さ、個別埋葬される期間などにより費用が大きく変わってきます。
・樹木葬型永代供養でかかる費用
樹木葬型永代供養の費用は3万円~150万円程です。
費用の内訳は霊園(墓地)使用料、納骨の際に必要な埋葬料、ネームプレートを設置する場合は彫刻料が必要になります。更に維持管理費が発生する霊園もありますが、施設によっては霊園使用料に含まれる場合もあります。
また合祀型・集合型の他、個別区画型など埋葬方法によっても費用が異なります。合祀型の場合は10万円~20万円程度、集合型の場合は20万円~100万円、個別区画型は50万円~100万円が費用目安となっています。
納骨堂型の永代供養でかかる費用
納骨堂型の永代供養を行う場合は費用は10万円~200万円程になります。
費用の内訳は以下4点。
・永代供養料
遺骨の管理・供養を納骨堂に委託する場合に必要な費用です。
・管理費
納骨堂の施設利用料で、永代供養料に含まれている場合もあります。
・法要料
法要時に支払うお布施のことです。永代供養料に含まれている場合もあります。
・戒名料
戒名をつけてもらう場合の費用です。
戒名がなくても弔ってもらうことはできるので親族でよく相談すると良いでしょう。
永代供養の支払い方法は?
永代供養の費用の支払い方法は契約する供養施設によって異なります。ここでは一般的ないくつかの支払い方法をご紹介します。
・一括払い: 契約時に全額を一度に支払う方法です。一括払いを選ぶことで、将来的な維持費用の心配を減らすことができます。
・分割払い: 契約料や費用を定期的な分割払いで支払う方法です。月々の支払いが軽減され、財政的な負担を分散させることができます。
・クレジットカード払い: 一部の供養施設はクレジットカードを受け付けており、クレジットカードで支払うことができます。これは一括払いや分割払いをクレジットカード経由で行う方法です。
・メモリアルローン支払い:すぐに支払えない場合、供養施設によってメモリアルローンが利用できる場合があります。
永代供養をする場合のメリット、デメリットは?
永代供養をする場合のメリット、デメリットや注意点をしっかり認識しておく事も重要です。
| 永代供養のメリット | 永代供養のデメリット |
|---|---|
| ・継承する人の有無に関わらず申し込みをすることができる ・一般的なお墓を建てるより費用が安い | ・遺骨がいずれ合祀されるため他人と遺骨が一緒に埋葬され、個人の遺骨を取り出すことができない ・施設により、線香が禁止などお参りの仕方を制限される場合がある |
永代供養の注意点
永代供養は個別型で契約した場合、一定期間(契約期間により異なる)を過ぎると複数の故人の遺骨と同じスペースに納骨されることが一般的です。合祀された後の遺骨は分骨ができないため、後から個別に墓を建てても取り分けをすることができません。
資金面などでいずれは個別墓を建てたいと考えている方は十分に検討することをおすすめします。
永代供養をしてもらえる期間は?
永代供養の期間は永遠ではありません。契約内容によって異なりますが、一般的には33回忌までとされています。契約によっては10回忌、50回忌というケースもあります。親族に継承させたい場合は永代供養とは別の方法を検討することをおすすめします。
永代供養の場合、お布施はどうなる?
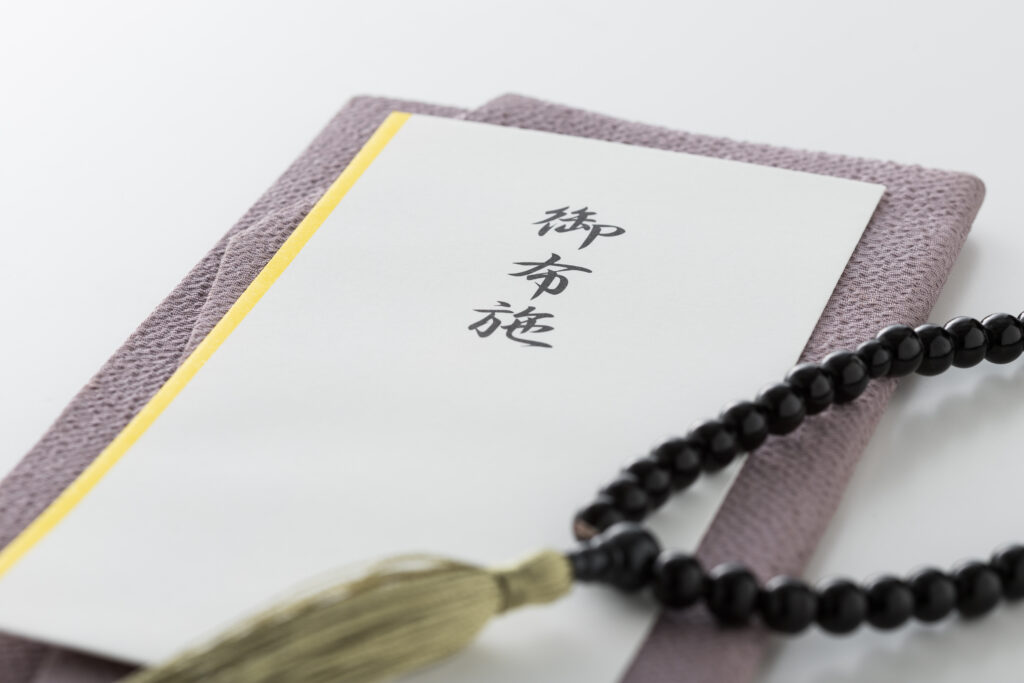
お布施は基本的に永代供養料に含まれている場合があるのであらかじめ確認することをおすすめします。年忌法要や個別に行いたい場合は別途お渡しする必要がありますが、永代供養のお布施相場は3万円~5万円程です。その他、自宅に来てもらう場合はお車代なども必要です。
永代供養の費用は誰が払う?
永代供養の費用の支払いは、通常、故人の家族や遺族によって行われます。契約料や維持費用は、供養を希望する家族や遺族によって負担されます。ただし、一部の場合では故人自身が生前に費用を負担し、あらかじめ契約を結んでいることもあります。具体的な支払い責任は契約内容や家族間での合意に依存します。
永代供養をお考えなら、死後事務委任という選択も
自分自身の死後、永代供養と考えている方には事前に準備をしておくことがおすすめです。葬儀や供養を事前に相談し、備えておくことができる死後事務委任サービスを利用してみませんか?
身寄りがない、親族に負担をかけたくないとのご相談も多くあります。葬儀など亡くなった後の手続きへの備えや対策についても、「行政書士法人アルド」にご相談ください。
監修

- 行政書士・弁護士
-
法的準備は、安心した生活の基盤になりますし、将来の手続負担の軽減にもつながります。手続きを知り、備えることで、自分らしく生きるきっかけになればと思い、生前のサポートを充実させることを大切にしています。
遺言書の作成や、死後の手続支援(死後事務委任)、不動産に関する手続きなどについて、相続専門の行政書士法人として、幅広く情報提供をさせていただき、一人一人の生活に合った選択肢を一緒に考えてきます。
最新の投稿
 永代供養2024年12月28日永代供養墓とは?種類や必要性、そして歴史・選び方まで徹底解説!
永代供養2024年12月28日永代供養墓とは?種類や必要性、そして歴史・選び方まで徹底解説! 葬儀2024年12月26日葬儀の流れを徹底解説。事前準備や基礎知識、葬儀社選び、葬儀後の手続きを紹介
葬儀2024年12月26日葬儀の流れを徹底解説。事前準備や基礎知識、葬儀社選び、葬儀後の手続きを紹介 お部屋の片付け・遺品整理2024年10月29日葬儀に参列する際に知っておきたい服装や香典のマナーを詳しく解説
お部屋の片付け・遺品整理2024年10月29日葬儀に参列する際に知っておきたい服装や香典のマナーを詳しく解説 葬儀2024年10月28日葬儀社選びのポイントは?サービスや費用について詳しく解説
葬儀2024年10月28日葬儀社選びのポイントは?サービスや費用について詳しく解説